
ニュースやSNSなどで「熊を駆除するのはかわいそう」といった声を耳にすることもあります。確かに、命を奪うことはかわいそうと思われる気持ちもわかります。
しかし、熊の駆除が行われなければ、人間の生活に被害が出ることも事実です。そこで本記事では、そもそも熊の駆除はなぜ行われるのか、その理由から熊の駆除の必要性を見ていきましょう。
さらに、共存を目指すためにどういった取り組みが必要とされるかについても触れていきます。熊と人間の環境を改めて考えるためにも、ぜひご覧ください。
なぜ熊が駆除されるのか?

まずは、熊が駆除される理由を見ていきましょう。大きな理由は以下の2つです。
- 人的被害があるから
- 農作物・家畜の被害があるから
人身被害の増加とその背景
熊による人的被害は、2023年度時点では全国で219人が熊による被害を受けており、この中で6人の方が亡くなっていると報じられています。
この背景には熊の個体数が増えており、山の食糧不足が起きていることが一因としてあります。
農作物・家畜への被害
基本的に熊は山の中で暮らしていますが、山の餌が少なくなってくる時期になると人里に降りてきて、家畜や農作物へ被害を及ぼします。
特に酪農や農作物が豊富に獲れる北海道では、2022年度に年間で2億7,000万円もの被害が出ました。
熊は簡単に餌が手に入る場所を知ると、その場に執着すると言われています。この習性から、同じ地域の農作物が被害に遭うことも少なくありません。
熊の生息環境の変化と人間の関係

では、どのように熊の生息環境が変化しているのかを見ていきましょう。
森林伐採と熊の生息域の縮小
森林伐採によって熊の生息域が縮小してしまうと、餌そのものの減少や熊同士の競争によって餌が不足してしまいます。
熊の個体数と山の餌のバランスが取れていないことで、食糧不足になり、十分な餌にありつけなかった熊は人里に降りてくるようになります。
食料不足による人里への出没
熊は山の食料が不足すると、生き延びるために人里へと降りてきます。特に秋は冬眠に向けて大量のエネルギーを蓄える必要がある時期であり、食料確保は熊にとって最優先課題です。
しかし、山の中ではブナやミズナラの実が不作だったり、草木の栄養価が低下したりすると、熊は十分な餌を得られません。
一方、人里には豊富な食料が揃っています。田畑にはトウモロコシや果物などの農作物が実り、一箇所でまとまって育っているため、熊にとっては「効率の良い餌場」に映ります。
山の中で分散して探し回るよりも、人里に行けば短時間で大量の食料を確保できるため、結果として熊の出没が増加するのです。
共存を目指す取り組み

近年では熊との共存を目指す取り組みも行われています。
熊の被害を受けにくい環境をつくる
熊との共存を目指すためには、被害を受けないよう準備を整えることが大切です。
例えば、キャンプ場の中には、食べ物に釣られて熊がやってこないよう、コンテナ型の食糧庫を用意している場所もあります。
さらに、持ち運びできるサイズのコンテナを用意したり、民家の近くにゴミ置き場としてコンテナを用意したりといった工夫が見られます。
人里への侵入を防ぐことはもちろんですが、人が山の中に入っても熊の被害にあわないように工夫することも大切です。
熊の生息地と人里の境界を明確にする
熊の生息地域と人間の生息地域を明確に区別することも重要です。特に河川敷などの草を伝って人里へ侵入することが多いことから、境界部分の草刈りが重要視されています。
都道府県によっては草刈りを行ったうえで電気柵を設置するなど、熊が侵入できないように区分けする自治体もあるほどです。
まとめ
熊の駆除は、人的被害や農作物被害の防止が主な目的です。
近年、熊の個体数増加と森林伐採による生息域の縮小により、食料を求めて人里に出没するケースが増えています。特に秋の収穫期には特に被害が拡大し、多くの地域で対策が求められています。
一方で、熊を駆除せず共存を目指す取り組みも進んでいるのが現状です。ゴミ管理の徹底や電気柵の設置、人里への侵入経路の整備などが有効な対策として実施されています。
また、キャンプ場や民家周辺では、食料庫やゴミ置き場を熊に狙われないよう工夫する動きも見られます。
熊との共存には、人間側の環境整備が不可欠です。適切な対策を行うことで、被害を減らしながら熊と共生する道を模索することが求められています。
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

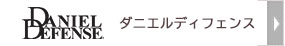





















コメントを残す